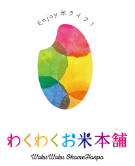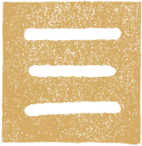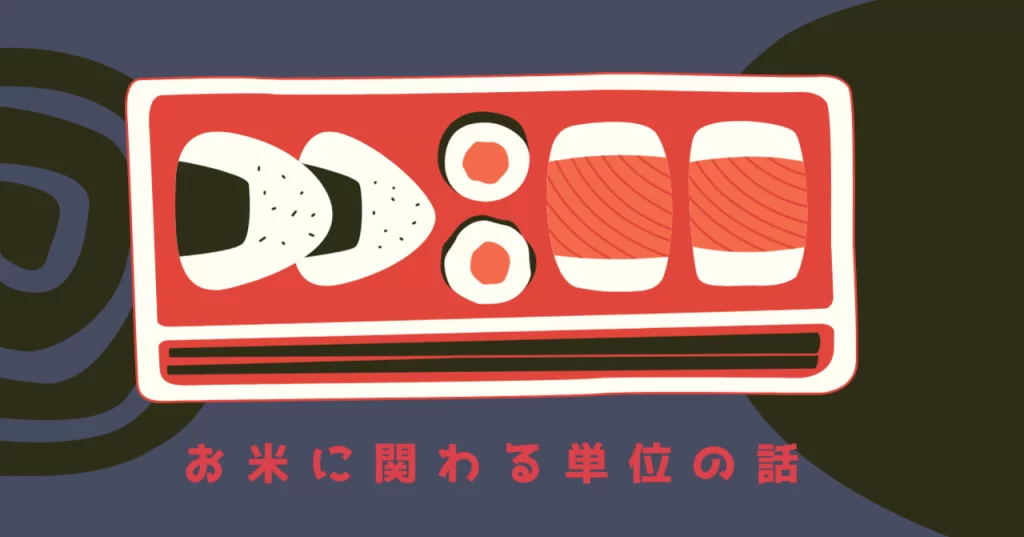
いろいろな単位
私が新規に就農した時に、まず戸惑ったのが面積を表す「町」や「反」、「畝」などの単位。いまいち広さがピンと来ませんでした。それ以外にもお米農家をやっていると、「ha(ヘクタール」「a(アール」「俵」「升」「合」などいろいろな単位と出会います。
その中でもなじみがなかったのが、「うちの米の乾燥機は23石の大きさだよ。」の「石(こく)」!
でも、確かに日本の歴史でも「加賀百万石」なんて言い方しますよね。または、「1万石以上が大名!」なんて習いました。いったいこれはどんな単位なのでしょう?今回はこの「石」について調べてみました。
豊臣秀吉の太閤検地
1石は、ずばり2.5俵、1俵が60kgだから、150kgです。もともと大人1人が1食1合×3食×1年間で食べるお米の量を1石としたそうです。いやいや、今やこんなにお米食べる人いないですよね。米農家の私でもこんなに食べません。パンやパスタも美味しいですもんね。
そもそも「石」が使われるようになったのは、豊臣秀吉の「太閤検地」から。その土地からどれぐらいのお米がとれるかを調べて、それを元に大名の国力だとか、戦時の兵の動員力とかを「全国統一基準」で決めたんですね。ちなみに1万石で兵隊の動員数は500名。なので、加賀100万石だと5万人の兵隊を出せる実力があるということですね。
江戸時代には武士の給料とかを表したりもしました。この仕組みが「石高制」で、明治時代の地租改正まで続きます。
「太閤検地」に始まる「石高制」は大名統制の意味もありましたが、画期的なのは今にも通じる面積や量の単位が全国的に統一されたことです。その時に決まったことをまとめると・・・・
土地面積の基準
- 1間(約191cm)
- 1間四方=1坪=1歩
- 30歩=1畝
- 10畝=1反
- 10反=1町
量の基準
- 1升=10合=1.8㍑=※で約1.5kg
- 1斗=10升=約18㍑=米で15kg
- 1俵=4斗=約72㍑=米で約60kg
- 1石=10斗=約180㍑=米で約150kg=2.5俵=大人の食べる米1年分
冒頭に書きましたが、農家をやっていると、「町」や「反」は今でも使います。その他の単位も家を建てるときに「坪」、日本酒が好きな人は「1升瓶」、わくわくお米本舗で使う米油は「1斗缶」に入っているなど、今でも生活の中で使われていますね。豊臣秀吉の時代にできた、こうした単位が今でも使われているとは驚きです。
さぁ、江戸幕府に就職してみよう!
そこでたいへんに気になるのが、私が武士で江戸幕府に勤めたらどんな役職に就けるかです。(気になるのは私だけ?)
わくわくお米本舗では農地が約10町歩あります。1反からコシヒカリを8俵とれたとして、10町だと800俵、48000kgになります。「石」に直すと320石になります。320石取りの「武士」になるわけです。(ざっとね。いろいろと細かいところは無視。)
うーん、1万石の大名にはほど遠い・・・しょうがないので、旗本を目指しましょう。できれば将軍に会いたい。目指せ、お目見以上!
遠山の金さんみたいにかっこいい「町奉行」!これは3000石かぁ・・・だめですね。300石レベルで付ける役職は・・・・お。町奉行配下の牢屋奉行が300石!うーん、牢屋かぁ。こわいなぁ、江戸時代の罪人。
400石あれば、幕府の所有する甲冑を管理する具足奉行が楽しそう。いや、楽しいのは最初だけ?ずっと甲冑の管理はちょっと。
勘定奉行配下の勘定組頭350石、金奉行の200石ならなんとかいけそう。お金の出納だから小判とか触れて楽しそうだけど、財務会計苦手だしなぁ。
私レベルだとあんまり仕事選べないですね・・・・思い切って、石高は関係ないけど、火付盗賊改になって「鬼平」こと、長谷川平蔵のもとで働こうかな。江戸の平和は私が守る!!でも、盗賊こわいし、なにより上司がこわい。
うん。やっぱり江戸幕府への就職はやめて、下野(栃木)にもどって普通にお米作ろう。農家がいちばんいいや。